2023-7-28
昨日の内に槍ヶ岳へ到達する予定でしたが西鎌尾根前で雷雨に遭い双六小屋まで撤退。夏山の午後は雷のリスクが跳ね上がりますね。反省を生かして本日は朝早いうちに槍ヶ岳へ登頂。天候が崩れる前に南岳小屋へ滑り込みます。
双六小屋の朝

おはようございます。暗いうちにテントを撤収し、現在は日の出を狙って小屋前でスタンバイしています。写真を撮ったらすぐ出発して10時までには槍ヶ岳の山頂を獲りますよ。午後の雷雨は昨日のでこりごりです。早め早めの行動を心がけていきましょう。
といいながら朝日の写真は逃せないのですが(▼∀▼)

日が昇ってきました。目が一気に覚めますね。美しい……。

左奥の一番高いのが唐松岳。その隣の平たいピークの山が餓鬼岳ですね。右奥はーー

燕岳ですね。表銀座の起点となる山で北アルプスの女王の異名を持つ美しい山です。ここから見ると全く印象が違います。



テント場方面には笠ヶ岳。贅沢すぎる立地ですね双六小屋は。

モルゲンロートの笠ヶ岳が美しい……。
裏銀座縦走四日目
4:55 双六小屋

満足しました。活動を開始しましょう。まずは昨日撤退した場所まで向かいます。一度通った所をまた登り返す億劫さったらないですね。゚(゚^ω^゚)゚。

双六小屋もどんどん人が起きてきて賑わってきましたね。

朝でもこれだけ日が昇ってしまうともう暑いです(^-^;
5:25 樅沢岳

双六小屋からのガレた登りを歩いて樅沢岳へ到着。

昨日は見かけなかったヘッドライトがかかっていますね。ナイトハイクしてここでご来光見た人の忘れ物でしょうか。

一度通った道なのでスイスイ行けます。
……と思った矢先に浮石踏んで尻もち。このサイズの岩が浮石だと……!

眼前の槍に励まされながら歩みを進めます。

まだ6時前だというのにこの陽の強さ。本当は暗いうちから動き始めるのが良いのでしょうけど夜は超気分が上がらないのでテントの撤収にも手間取ります。゚(゚^ω^゚)゚。

荒々しい赤い岩肌が特徴的な硫黄尾根も日が当たらないとあまり目を引きませんね。時間帯によって同じ場所でも大きく印象が変わるのが山の面白いところ。同じ山に何度も登ってしまう理由ですね。好きで二回もこの道を渡っているわけではありませんが(メ゚皿゚)

この道を越えると
6:10 撤退ポイント

昨日撤退したポイントです。テント張ろうか迷ったのも分かる立地でしょう? 水も雨水や雪渓で何とかなるな、と思ったら中々離れられませんでした。゚(゚^ω^゚)゚。
結局は勇気の撤退でしたけどね。良い判断だったと思います。ここからが昨日の続き。その前に少し休憩していきましょう。

笠ヶ岳は今日も立派。

百名山が三つ写っていますね。

奥が乗鞍岳で、その手前が焼岳です。焼岳をこの方角から見たのは初めてです。火山らしい荒々しい山容で、登ったことがあるのにとても新鮮に感じます。自分が登ったことのある山を他の山から眺めるというのも登山の醍醐味だよなとつくづく実感します。

焼岳の手前は西穂高から新穂高温泉へ下りるロープウェイですね。現在調整中で8/9まで止まっていますが。

さて、休憩を終えたら昨日敗退した西鎌尾根へ突入です。長いこと視界に入っていた槍ヶ岳。とうとうそこに至る尾根へ取りつきますよ。

鎖場も出てきました。慎重に行きましょう。

ドキドキよりもワクワクが勝る縦走路。素晴らしいですね。しかしーー



 ほこから
ほこから間違い探し?
ってくらい同じ構図で写真を撮っていて笑いました。同じ構図なのに見るたびに感動してシャッター切ってしまいます。


鎖もあるっちゃありますが使わなくても登れるくらいの難易度ですね。


宝剣岳を思い出します。




どんどんやりが近づいてくるこの興奮感!
遠くから見たおなじみの天を衝くかのようなシルエットが近づく度に崩れていきます。ずっと見ていた山なのに接近するにしたがって新しい顔になっていく面白さ。早く頂に立ちたい……!


槍ヶ岳から降りてきた山岳部の学生さんとすれ違い。平日と言ってももう夏休み期間ですからこういった部活動で来ている学生さんをチラホラ見かけますね。
一週間以上の大縦走は部活としてじゃないと中々やる機会はないだろうなぁとふと思いました。あと私の様な無職とか。サラリーマンになってから登山にハマると長くてもせいぜい3泊が良いところですもんね。一カ月以上の山籠もりとかとても憧れます。
そういうレベルの登山になるともう趣味ではなく何かの活動の一環としてじゃないとなかなかできないなと感じます。誰にとっても身近な活動が部活動で、同志と共に長期間山に入れるのは学生の特権かもしれないとシミジミ思ったりしました(。◔‸◔。)
7:55 千丈乗越


千丈乗越到着。ここからエスケープルートとして飛騨沢に下ることもできます。


千丈乗越に着いたらちょうど太陽が槍の上に。うしおととらの名シーンだ。
獣の槍 pic.twitter.com/GpQ1C4XJAm
— ほこから@日本一周336日目 (@fawtMT) July 27, 2023


南側に見えるこの道がちょっと衝撃でした。こんなルートがあるんですね……。飛騨乗越へ至るルートでしょうか。


千丈乗越からは槍ヶ岳まで標高差360mの中々にキツイのぼりが始まります。ドーピングして進んでいきましょう。


槍を指すペンキを頼りに進みます。


ただひたすら進むのみ。





あああああ!!!!!



槍!!!
とうとう槍の直下に。゚(゚^ω^゚)゚。


槍ヶ岳山荘も見えてきました!
9:05 槍ヶ岳山荘


槍ヶ岳山荘
到 着 !


Twitterでめちゃくちゃ見た槍ヶ岳山荘だ! 感動(っω<。)
有名な山だけにSNSでは毎週のように見るこの景色。自分の目で見ることができる感動ったらないですね。


ライブカメラ先輩チィース!!!
2023年07月28日 09時00分 時点で最新の槍ヶ岳のライブカメラ画像です。 pic.twitter.com/obyxoWw28z
— 槍ヶ岳ライブカメラ (@LivecamYari) July 28, 2023
一時間ごとに槍ヶ岳の景色をツイートしてくれるライブカメラ先輩にようやく直接会うことができました。私も先輩に倣ってーー


2023年07月28日 09時00分 時点で最新の槍ヶ岳の一眼カメラ画像です。
これがやりたかった。満足です( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )


ではベンチに荷物を下ろして身軽になったら挑むとしましょうか。


槍の頂へ!


遠くから見ていた時点でわかる様になかなかに高度感のあるスリリングな道。頂上までのルートは一部共有していますが基本的には上り下り別ルート。これは登る人と下りる人が入れ違うのは難しそうですからね。落石も怖いですし。


三点支持を守ってしっかり注意深く登っていきます。恐怖感としては石鎚山の3の鎖の方が怖いので特にひるむことなく登れました。


ただやっぱり怖いからと途中で槍ヶ岳山荘に引き返す方もいましたから本当に個人差。無理のない範囲で山頂を目指しましょう。
9:30 槍ヶ岳


念 願 の !



槍ヶ岳!!!
登頂です!
嬉しすぎる!。゚(゚^ω^゚)゚。
長野で登山を始めておきながら6年以上も放置していた北アルプスの盟主。その山に日本一周中に訪れることができるとは。しかも槍へ至るルートの中で最も長大な裏銀座という贅沢なコースを歩いてです。感無量としか言いようがありません。


他の登山客の方にお願いして写真撮影。この祠もよくSNSで見ていました。まさか隣に立って写真を撮る日が来るとは。


この祠は雷を避けるために釘が一本も使われていないんですって。面白い。


標識はめちゃくちゃ新しいですね。今年の四月に新調された4代目とのこと。写真だけ撮ったらすぐ退きます。


槍ヶ岳の山頂は槍の穂先とも呼ばれますが本当にそれほどの面積しかありません。写真撮影の時には行列ができることもあるとか。平日でよかったです。


穂先からの展望は絶景としか言いようがありません。北アルプス屈指の大展望。私が歩いてきた裏銀座方面を始め


穂高に


笠ヶ岳。いくらでも眺めていられそうな素晴らしい景色が広がっています。
表銀座の方がガスっていて見えないのが少し残念。10時にはもうガスが湧きだすので夏山は朝が勝負ですね。




槍ヶ岳山荘がはるか下( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )


ちょうどヘリコプターが物資の搬入に来ました。






ヘリ先輩ご苦労様です。荷物を下ろすところ初めて見ました。


少し西に目をやると小さな突起があります。


これは槍ヶ岳の小槍です。童謡の「アルプス一万尺 小槍の上で~」の小槍はこれの事を指します。


ここでアルペン踊りを踊るのは至難ですよ~。



そもそもアルペン踊りってなんだろう……
一尺が約0.3030mなので一万尺は約3030m。槍ヶ岳の標高が3180mなので完全に槍ヶ岳の事を歌った曲ですね。アルプス一万尺は槍ヶ岳のキャラソン。


山頂でまったりしていたらだいぶ混んできました2時までには今日の寝床についておきたいのでそろそろ下りますか。


下りで結構渋滞してしまっていますね。梯子なんかは前の人が下り切った後に使わないと怖いですから時間がかかってしまいます。


急ぐと事故るのでゆっくり待ちながら下りていきましょう( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )




何とか山荘まで下ってきたら完全にガスの中。今日も昼から一雨来そうですね。


行動食をコーラで流し込んだら出発します。槍から離れるのは名残惜しいですね。この山を道標にこれまで北アルプスを歩いてきましたから。


裏銀座コースの終点である槍ヶ岳へたどり着きましたから後は下山というのがスタンダードな裏銀座縦走。横尾を経由して上高地に下りるのが最もオーソドックスでしょうか。
しかしこれは日本一周の一環としてやっている登山です。北アルプスをこれで下りるのはもったいなすぎます。という事でここからは新章へ突入です。北アルプス裏銀座縦走改めーー
北アルプス穂高連峰縦走
北アルプス穂高連峰縦走編の始まりです!( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )
日本の山岳にで標高3000mを越える山は21座ありますが、北アルプスの南部である槍・穂高連峰には槍ヶ岳を始め奥穂高岳など8座の3000m超山が集中します。そんな穂高連峰は国内最大級に切り立った岩稜帯が連なるアルピニスト憧れの山域です。


ゴール地点は新穂高温泉。行程的にはあと二泊で行けます。
が、穂高は本当に油断ならない山域です。裏銀座はコースが長い分体力的にはハードなコースですが技術的に困難な箇所はそうありません。
対して穂高は危ない!マジで。新穂高温泉へ下りるまでに難所がいくつかありますがそれ全てに挑む資格が今の私にあるかは分かりません。これまでの旅で培った登山経験的に行ける気はしているのですが所詮は主観的な自己評価。幸いルートは沢山あるのでこれから通る難所で少しでも恐怖を感じたらリタイアして最寄りのルートから下山しようと思います。
それくらいの気持ちでいないと命を落としかねない場所なのです(・`_´・)


休憩が終わったら移動開始。槍ヶ岳のテント場を横切ります。


ここのテント場もなかなか攻めた場所にありますね。一度泊まってみたかったですが槍ヶ岳はまた機会がある気がします。今度は表銀座から来たいですね。


では名残惜しい槍を離れて穂高へ向かいます。世界観いきなり変わり過ぎでしょう。゚(゚^ω^゚)゚。
デカい岩をまとった岩稜地帯。これまで以上に気を引き締めていきますよ。
まずは写真の鞍部の飛騨乗越へ。そこからは大喰岳への登り返しになります。


槍ヶ岳から穂高までの縦走は岩稜地帯が続く国内屈指の縦走路。前半の南岳まではゆったりとしたコースを行きます。これでゆったりです。怖いね穂高。
今日の目的地もその南岳を越えた先にある南岳小屋です。


槍がまたどんどん離れていきます。さらば槍。また会う日まで(´;ω;`)




昨日の事がありますから昼にガスると怖いですね。まだ雷鳴は聞こえませんが早いうちに小屋に着きたいところです。


大喰岳の標識が見当たりませんでしたが見逃した?
地図的に微妙に捲いている、か。ピークは通らなかったのかもしれません。


なんて綺麗なピラミッド型よ。これは常念岳ですね。公共交通機関でのアクセス手段が無い百名山なので登るか迷っている山です。表銀座ルートなら常念を絡める歩き方も可能なのですが。
12:40 中岳


梯子や鎖を超えて中岳へ。


再びヘリ先輩が出動しています。お疲れ様ですm(__)m
中岳からはカールをジグザグと大きく下って行きます。


馬の背状の尾根に沿って伸びる縦走路を進みます。雲行きが怪しくなってきましたね。
13:30 天狗原


天狗原到着。非対称の山稜で、なだらかな飛騨側の道を進んで南岳へ向かいます。


長野側は晴れていますが


飛騨側は真っ白。そろそろ一雨来そうです。


ライチョウ発見。雷の前触れかな?
13:50 南岳


南岳の山頂に到着。ここまでくれば小屋はすぐです。


下り始めてすぐに小屋が見えますからね。何とか天気が崩れる前に行動終了できる、と思った矢先に雷鳴が轟いてきました。
14:10 南岳小屋


滑り込みセーフ!!!
小屋に着いた瞬間土砂降りでした。゚(゚^ω^゚)゚。
見計らっていたかのようなタイミング。危なかったですね。やはり夏山の午後は危ない。槍周辺は特に崩れやすい気がします。
しかし滑り込みセーフは良いですが雨が止むまではテントも張れませんね。受付を済ませたらしばらく玄関で様子を見ておきますか。ここもテントは一張2000円です。
水は雨水をためたものが1リットル200円で売られています。煮沸するので問題なしです( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )


16時ごろにようやく雨が落ち着きました。少し肌寒いですね。ササっとテントを張って中でくつろぎます。


テント場はドコモの電波があまり入らないので通信が快適な場所を求めて少し散歩。せっかくなので小屋の南側にある大キレット展望台をちょっくら見てみます。


これが大キレットです。キレットとは「切戸」と書く日本語です。稜線が深く切れ落ちた急峻な地形の事を指します。英語で言うとギャップですね。
ここは「大」キレットというだけあって北アルプスの中でも指折りの難所です。明日通ります。
大キレットは南岳と北穂高岳の間にあるキレットでここを越えてようやく穂高の一角にたどり着くことができます。穂高連峰縦走の最初の試練ですね。ここでビビったならその先を歩くことはできないでしょう。
実は槍ヶ岳の梯子も試験のつもりで登っていました。あそこで恐怖を覚えたならここには来ないでおこうと思っていたのです。今ここにいるという事はそういう事ですが。少なくとも大キレットに挑戦するくらいの力はある、はずです。あとは油断しないこと。何処を歩くのもそうですけどね。実際に挑むべき壁を見ると引き締まるというものです。


挑戦の前には疲れを残してはいけません。夕食を済ませたらもう寝ましょう。


夕景の写真もこれで十分でしょう。


というか南岳小屋はテント場の立地が贅沢すぎますね。労せずこんな夕景をテント場から撮れるんですから。今日は憧れの槍ヶ岳に登って、最後はこの黄金の様な夕焼け。良い日でしたね。明日も良い日にしますよ。待っていなさい大キレット……!
ここまで読んでくださってありがとうございます。
よろしければ以下のバナーをクリックしていただけると大変励みになります。
↑日本一周バナー


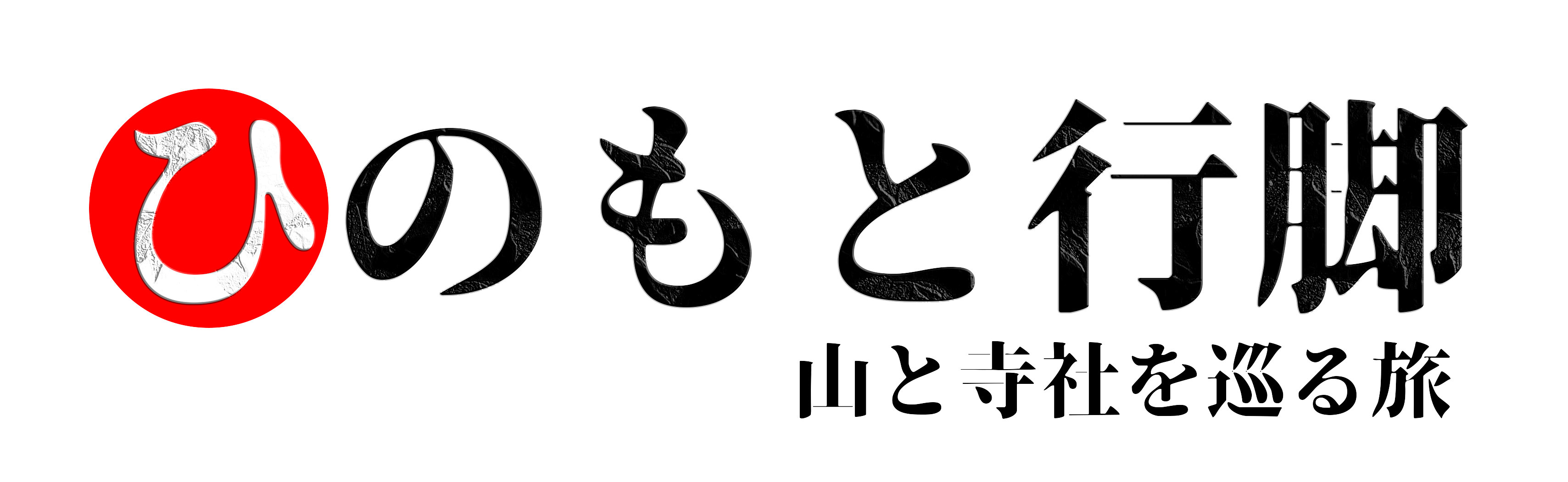




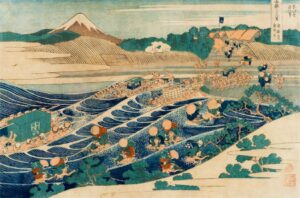







コメント